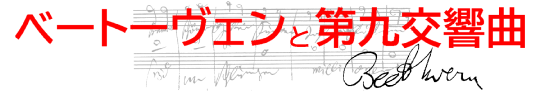日本における第九
第一楽章 日本における第九
話は100年以上前の大正時代にさかのぼる。
1914(大正3)年7月28日、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発した。三国同盟(ドイツ、オーストリア・ハンガリー、イタリア)と三国協商(イギリス、フランス、ロシア)との戦争である。当時の日本はイギリスとの日英同盟があり、また極東平和の回復を名目に三国同盟のドイツに対し宣戦を布告し、ドイツが租借する中国山東省のチンタオ(青島)を攻撃した。日本軍3万人とイギリス軍8千人の連合軍の前に、ドイツ軍約5千人は11月7日全面降伏した。
ドイツ捕虜4,715人は日本国内の12か所の収容所に護送され、そのうち千人あまりは1917(大正6)年4月徳島県板野郡板東町に建てられた俘虜収容所に集められた。捕虜の中には優秀な技術を持つ者も多く、「このたびのドイツ捕虜の中には、学者技術専門家など少なからずにつき、指導を受けたい者は申し出よ」と布告が出たほどである。板東収容所では地元住民との交流もあり、トマト・玉ねぎをはじめとする西洋野菜の栽培、ドイツパン・ドイツ菓子・ハム・ベーコン・ウィスキー・ブランデーの製造、鉄棒体操・レスリング・サッカー・テニス・ホッケー・ボウリング、そして演劇や音楽活動等が広められた。音楽活動では、①トクシマオーケストラ、②エンゲル・オーケストラ、③シュルツ吹奏楽オーケストラ、④Ⅲ・S・B吹奏楽団、⑤マンドリン楽団、⑥モルトレヒト合唱団、⑦ヤンセン収容所合唱団の7つが、それぞれ40から60名程度で活動していた。
板東収容所の所長は、旧会津藩士の子弟松江豊寿(1872(明治5)年-1956(昭和31)年)が務めた。会津藩は明治維新後の戊辰戦争に敗れたため、敗者のつらさを知っており、捕虜の扱いは正真正銘の武士の情けであった。収容所といえどものちの歴史で知られるナチスやシベリアのそれとはイメージが程遠い。収容所には日本の商人が出入りし、常設レストランがあり、地域住民には楽器を教え、捕虜に対しては本国ドイツから給与も振り込まれていた。トクシマオーケストラは35回、エンゲル・オーケストラは23回の演奏会を開催した。
「第九の日本初演」は1918(大正7)年6月1日(土)、トクシマオーケストラと男声合唱団80人がこの収容所において行った。
指揮はヘルマン・ハンゼン、捕虜の平均年齢は29歳前後。男声にあのソプラノが出せたのか、編曲していたのかは定かではない。数回の「第九」演奏会が催され、「音楽の殿様」と称されていた紀州徳川家16代目の当主徳川頼貞(1892(明治25)年-1954(昭和29)年)も、鑑賞するために東京からわざわざ訪れた。徳川頼貞は「中には2・3人音楽家がいるだろうが、多種多様な職業を持つ者が軍人として駆り出されているので、この素人たちが音楽芸術に対してこれほどまでに興味と理解を示していることに敬意を表したい。彼らにこの教養を与えたドイツ文化に羨ましさを感ぜずにはいられなかった。」と述べている。1918(大正7)11月11日戦争は終結し、板東のドイツ人の多くは祖国へ帰っていった。日本に残った者にはその後洋菓子店を営むユーハイムなどがいた。
次に期待する日本人による「第九」初演は、先に板東でドイツ人の「第九」に感動した「音楽の殿様」が活躍する。徳川頼貞の南葵音楽文庫には1917(大正6)年にロンドンで落札した「ワーグナーがロンドンで指揮した「第九」の初版楽譜」が含まれていた。
ベートーヴェンの「第九」初演から100年後の1924(大正13)年、当時の東京音楽学校(のちの東京芸術大学)には作曲科、楽理科、管楽器科が無く、管楽器部門については海軍軍楽隊から応援を得ることとなった。指揮者をはじめとする約200名が約半年間週2回の練習に励み、徳川頼貞はそのパトロンとして経済的援助を行った。ラジオ放送も始まっていない時代で、多くは「第九」が何であるか知らなかったであろう。それでも「第九」初演100年という節目は、ドイツからブルノ・ザイドラー・ウィンクラー指揮、イギリスからアルバート・コーツ指揮のいずれも(天然樹脂で固めた)シェラック盤レコードの「第九」が相次いで輸入され、日本では初演1週間前に田村寛貞訳著「第九ジュムフォニー」が出版され、「第九」フィーバーだったに違いない。
日本人による「第九」初演は、1924(大正13)年11月29日(土)に行われ、翌30日(日)も行われた。
演奏会場は、上野にあった東京音楽学校の座席数388の奏楽堂、指揮グスタフ・クローン、ソプラノ長坂好子、アルト曽我部静子、テノール船橋栄吉、バリトン沢崎定之、東京音楽学校のオーケストラと学生全員による合唱である。「ベートーヴェンの傑作「第九シンフォニー及び合唱」はわが国最初の快挙」という触込みに、わずかな切符は完売し、この素晴らしい音楽熱に動かされて、12月6日(土)に再演が決定したことを当時の報知新聞は伝えている。演奏は混乱したようだが、それでも「第九」を始めて聞いた人々のその音楽熱は数々の逸話となって後世に伝えられている。
1925(大正14)年3月、楽壇の麒麟児と呼ばれた山田耕筰(1886(明治19)年-1965(昭和40)年)は日本交響楽協会を結成し、近衛秀麿(1898(明治31)年-1973(昭和48)年)の協力を得て、新しいオーケストラ活動を展開した。結成直後の1925(大正14)年4月、東京歌舞伎座でロシア人楽団員34名と日本人楽団員38名による「日露交歓交響管弦楽演会」を開催し「未曽有の壮挙」と言わしめた。
1925(大正14)年7月12日、東京放送局(のちのNHKラジオ)が設立されラジオ放送が始まった。この放送開始日に日本交響楽協会は近衛秀麿指揮でベートーヴェン交響曲第5番などを演奏した。日本交響楽協会は1926(大正15)年1月から定期演奏会を開催したが、様々な事情で分裂し近衛秀麿と大多数が行動を共にし、1926(大正15)年10月5日、新たに「新交響楽団(新響)」を結成した。
新響は、ベートーヴェン没後満100年にあたる1927(昭和2)年5月3日から6夜にわたって日本青年館で行われた「ベートーヴェン百年祭記念大演奏会」の中で、日本人による2回目の「第九」演奏を行った。指揮は近衛秀麿が務める予定だったがチフスを患い、「日露交歓交響管弦楽演会」に参加していたプラハ生まれのヨゼフ・ケーニヒが指揮した。
新響はこの後、太平洋戦争開戦まで34回、戦時中20回「第九」を演奏している。山田耕筰はそのうち1935(昭和10)年と1937(昭和12)年に1回ずつ「第九」を指揮している。「新響も設立当初は分裂や融合、外部から新しい風を吹くこむことを繰り返しており、その後の群響の草創期とまるで同じようであった。」と山田耕筰は後に述べている。ちなみに山田耕筰は、群馬交響楽団(群響)草創期の高崎市民オーケストラの葛藤を描いた「ここに泉あり」で「第九」を演奏しており、山田耕筰の名演が今なおフィルムに焼き付いている。
新響は1942(昭和17)年5月1日「財団法人日本交響楽団(日響)」と名称を改め、山田一雄と尾高尚忠を補助指揮者とした。戦時中、ドイツは日本の同盟国であるために、「第九」が敵性音楽とされることはなかったが、学徒出陣を奮い立たせる壮行会において運悪く「第九」が使用された。これは、当時のナチスドイツでもフルトヴェングラーが何度かナチス政権のために「第九」を指揮している。そこに歓喜はなかった。
1945(昭和20)年8月15日、終戦を迎えた。日本はほとんど再起不能を思わせるほどの大打撃を被っていた。特に首都東京は相次ぐ空襲で焼けただれ、都市機能は極度に低下していた。しかし、終戦からちょうど1か月後の1945(昭和20)年9月14日(金)・15日(土)に、戦後第1回の日響定期演奏会が日比谷公会堂で行われた。
当日は、尾高尚忠の指揮でベートーヴェン交響曲第3番「英雄」などが演奏されたが、当時の状況から考えるとその立ち直りの早さは、まさに「英雄的」で賞賛に値するものだった。しかし、本当の意味での再建には程遠かったようだ。楽団員の中にはいまだ復員しない者もあり、病気や生活の立て直しで落ち着かぬ楽団員もおり、時たま新聞に出る演奏会の評判も、あまり芳しいものではなかった。また、当時は連合軍による占領下であったため、日比谷公会堂もその管理下に置かれ、夜間は使用できず、すべての音楽会は午後の開催となり、聴衆にとっては極めて不便であった。
戦後第1回目の「第九」は、1946(昭和21)年6月の定期演奏会において、ローゼンシュトック指揮により行われた。
「暮れの第九」のはしりは、1947(昭和22)年12月13日(土)から3日間にわたって演奏された「第九」がきっかけとなった。
日比谷公会堂で行われた演奏会は、指揮レオニード・クロイツァー、ソプラノ大熊文子、メゾソプラノ四家文子、テノール柴田睦陸、バリトン中山悌一、合唱東京高等音楽院・玉川学園・みどり会で、この「第九」は相当に熱情あふれるものであったらしい。
敗戦から未だ2年足らず、焼け跡にはバラックや闇市が立ち並び、食糧不足や急激なインフレ(1945年10月から3年半で物価は約100倍上昇)は市民生活を極度に低下させ、労働争議が頻発し、巷には「星の流れに」などのやるせない流行歌が流れていた。「日響」の楽団員とて生活の厳しさは変わることがなかった。このような状況の中での「暮れの第九」は、まさにこの楽団員の越年資金を確保するためのものであったとも伝えられている。その後の「日響」の「暮れの第九」は毎年続けられ、この習慣は1951(昭和26)年、1961(昭和36)年のみ中止され、いまだに続いている。
日響は1951(昭和26)年8月1日「NHK交響楽団」と名称を変更する。
<つづく>